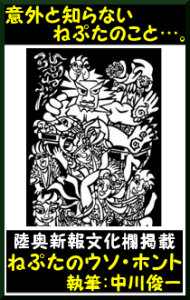- ホーム
- おもいで
カテゴリー:おもいで
-

2015の思い出ー写真集ー10ー暫の顔面
2015年の本ねぷたのモチーフの歌舞伎十八番 暫です。 今回は面の骨組に趣向を凝らしました。 ここ数年、歌舞伎の題材をよく制作しているのですが、 いつも、頭を抱えるのが「墨入れ」なんです。
-

2015の思い出ー写真集ー9-台湾の花燈制作技法の活用
台湾にも、ねぷたのような人形灯籠があります。 その名も「花燈」 両者には、様々な違いがあるのですが、 写真にある人形ねぷたの一部に、台湾方式を活用してみました(^。^)y-.。
-

2015の思い出ー写真集ー8-男子高校生の「一歩、前へ」
今年は、男子高校生や新卒者など、ヤングな男子の新顔が多く参加しました。 今日は、そんなヤング男子の思い出。 運行初日のことでした。
-

2015の思い出ー写真集ー7-新しい仲間
Hissatsuねぷた人には、毎年新しい仲間との出会いがあります。 写真は、書家の大ちゃんの長男「タケル」です。
-

2015の思い出ー写真集ー6-自慢の子どもたち
2015年は、子どもたちが新たなステージに挑戦した年でもありました。 中学1年生のリサは、人形ねぷたの台座部分の絵のデザイン・配色を担いました。 小学校6年生のレイラは、本ねぷたの額絵を3枚書き上げました。
-

2015の思い出ー写真集ー5-チャレンジングな秘策
2015年は、新規の高校生が多く参加しました。 最近の傾向ですが、若年層の参加理由が「友達に誘われたから」に偏っていますね。
-

2015の思い出ー写真集ー4ー前ねぷたの絵師は高校一年生
前ねぷたの絵師は、高校一年生の白取瀬凪!(^^)! 彼が、うちの前ねぷたを描くのはこれで8年目になりました。 高1で八年目??? そうなんです。彼の前ねぷたデビューは小学校3年生でした。
-

2015の思い出ー写真集ー3-本ねぷたの台座
HIssatsuねぷた人の台座は、絵の模様・構図は伝統的な様式を踏襲していますが、 配色は、モダンです。 伝統的な配色は、赤をメインに、補色の濃い緑、差し色に黄色を用います。
-

子どもたちと一緒にねぷたを楽しむ全く新しい方法
我々のねぷた団体では、子どもたちの参加をいつも大歓迎しています。 様々な用意をしています。 ねぷた制作時は、いつも子どもたち専用の安全な作業内容と作業場所を確保しています。
-

昨日の夕方の出来事
最近、うちの三才になったばかりの娘がトイレトレーニングを頑張っている。 しかしながら、やはり興奮すると我慢ができず、一昨日の夕方もウンチおもらしをしてしまった。
-

ねぷた組師にとっての墨入れという作業
組ねぷた=人形ねぷたを作る人間にとって、「墨入れ=書き割り」という作業は特別なものである。 それは、墨入れの作業が人形ねぷたの優劣を決めると言われているからだけではないと思うのだ。
-

ねぷた運行における子どもたちの安全確保のために①前灯籠
最近、子ども連れの交通機関など「公の場」での、マナーについて様々な報道・議論があります。 この議論を、ねぷた運行について考えてみたいと思います。
-

2014年8月6日の追想録
弘前経済新聞にて記事にして頂きましたが、 昨年の8月6日に我々のねぷた団体は、ねぷたを小屋から出しました。 賛否の声に配慮し、これまで自らのHPに記録を残さないできました。
-

ねぷた小屋は子どもたちの居場所になり得るか?
最近、地域社会と子どもたちに関する気になるニュースが3つほどありました。 ①公園で子どもに「こんにちは」とあいさつした男が不審者として、通報され注意喚起情報が公開される。
-

ねぷた小屋という居場所=サードプレイス:第三の場所―安全の根底にあるもの
サードプレイスという言葉があります。 アメリカの社会学者の方が、1989年に初めて提唱したものです。
-

ねぷた団体という組織の運営「ワンマンによる決定か?グループでの合意形成か?」
ねぷた団体は、基本的にボランティアな組織です。 一般的な会社組織とは異なり、参加する事でみんながみんな給料をもらえるわけではありません。
-

「芸術表現としてのねぷた」
昨日の続きです。 ねぷたが「まつり」になったのは、いつだか知っていますか? ズバリ、戦後です。「弘前ねぷたまつり」という名称が正式に決まったのは昭和33年のことです。
-

2014の思い出ー写真集ー28「歌舞伎の精神性」
うちの団体は、弘前では珍しく、歌舞伎を題材にねぷたを作ることが多いでのです。 ところで、「歌舞伎=かぶき」という言葉の語源を知っていますか? 実は、漢字は当て字なんだそうです。 語源は、「傾く=かたむく」なんです。
-

2014の思い出ー写真集ー27「人と人をつなげる確かな力」
一枚目は、昨年の浅草ねぷたの際に、浅草の方が開いてくれた振る舞い酒の宴席です。 100人以上が西参道通りというアーケードの下、数十メートルにわたって、ともに酒を飲みかわします。
-

懐かしの写真集ー2007-1「Hissatsuらしさとは?」
写真は、2007年の人形の前ねぷたです。 この年も、地震が多く発生した年でした。 なまずを踏みしめ、地震を鎮めようと笛を吹く男を制作しました。 さて、このねぷたを作るときに考えたことを全て挙げてみましょう。