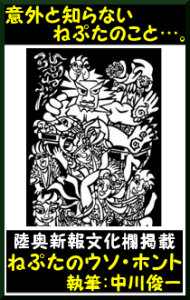- ホーム
- 過去の記事一覧
過去の記事一覧
-

組ねぷたクイズ第22問
弘前ねぷたまつりでは、2014年度4つの団体が本ねぷたを組ねぷた様式で制作している。 また、前ねぷたを組ねぷた様式で制作している団体が8つある。
-

組ねぷたクイズ第21問ー解答
答え:✖ 団体ごとに様相は異なるが、分業されている事例も多い。(もちろん、分業していない事例も存在する。) 近隣の組ねぷた制作事例では、全て一人で行う方も多い。
-

組ねぷたクイズ第21問
組ねぷたの制作には、骨組みを組む組師、表面描写を施す絵師、書を揮毫する書家という専門的技能が必要となる。 弘前ねぷたまつりにおいて、これらの3技能は分業されることなく、各団体ごとに一人の技術者が担っている。
-

組ねぷたクイズ第20問ー解答
答え:✖ ちょっと難しすぎましたか? 名称に誤りはないのですが、順番が一つだけ違うんです。 正しい順番は、額、開き、板隠し、蛇腹、高欄、となります。
-

組ねぷたクイズ第20問
弘前ねぷたまつりにおける組ねぷたの台座は、下から順に、額、開き、蛇腹、板隠し、高欄という名称がついている。
-

組ねぷたクイズ第19問ー解答
答え:○ 組ねぷたの台座部分の絵は、一般的な本ねぷたサイズで200枚を軽く超える。 採寸、紙断ち、ロウ引き、色付けと作業は進められるが、作業量は「紙貼り」に次いで多い。 (組ねぷたの作業の大半は「紙貼り」であると言われる。
-

組ねぷたクイズ第19問
組ねぷたの台座部分の絵は、一般的に本ねぷた一台あたり200枚以上である。
-

組ねぷたクイズ第18問ー解答
答え:✖ クイズが、色付けの作業領域に入ったところでのこの問題はズルいですね。 そうなんです。このような半透明の描写にはロウを用いるのです。 ロウの効果については以下にまとめています。
-

組ねぷたクイズ第18問
組ねぷた表面の半透明な質感(白目、爪など)の描写には、水性絵の具を用いて極薄い灰色を作り表現される。
-

子どもたちと一緒にねぷたを楽しむ全く新しい方法
我々のねぷた団体では、子どもたちの参加をいつも大歓迎しています。 様々な用意をしています。 ねぷた制作時は、いつも子どもたち専用の安全な作業内容と作業場所を確保しています。
-

組ねぷたクイズ第17問ー解答
答え:○ 組ねぷたは、その内部に照明を配置した立体造形である。 それゆえ、内側から光を発する「発光体」である。 一般に、立体的な造形物はそれ自体が光を発することは無い。
-

組ねぷたクイズ第17問
組ねぷたの着色には、発光体特性を考慮して、ぼかし(グラデーション技法)を多用する。
-

昨日の夕方の出来事
最近、うちの三才になったばかりの娘がトイレトレーニングを頑張っている。 しかしながら、やはり興奮すると我慢ができず、一昨日の夕方もウンチおもらしをしてしまった。
-

組ねぷたクイズ第16問ー解答
答え:✖ 旧来は、より光の透過率の高い染料が、次いで顔料が用いられてきた。 しかし、現在では、上記以外にも様々な塗料が用いられる。
-

組ねぷたクイズ第16問
組ねぷたの着色には、染料と顔料しか用いない。
-

組ねぷたクイズ第15問ー解答
答え:○ ロウは主成分が油分、クレヨンも主成分は油分なので混ぜ合わせることができる。 クレヨンをカッターや鉛筆削りで細かくして、ロウに溶け込ませていく。 しっかりとした色味をつけるには、同色のクレヨンが複数本必要となる。
-

組ねぷたクイズ第15問
組ねぷたの描写に用いるロウにクレヨンを混ぜると色付きのロウができる。
-

組ねぷたクイズ第14問ー解答
答え:○ 組ねぷたの彩色に用いるロウは、主成分が油分である。 熱を加えることによって、液化して粘度が低くなり、和紙の裏表に浸透する。 この際の適温は130度ほどと言われている。
-

組ねぷたクイズ第14問
組ねぷたの描写に用いるロウは、発火した際に水で消火できない。
-

組ねぷたクイズ第13問ー解答
答え:✖ かすれを活かした筆さばきである渇筆のとは逆に、かすれを残さない潤筆という筆さばきがある。 一昔前ならば、「青森は潤筆、弘前は渇筆」という声も多かったが、 現在では、弘前でも潤筆を部分的に用いるのが一般的である。