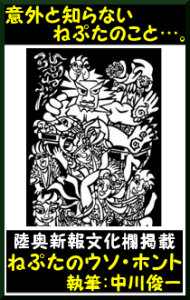坂上田村麻呂をねぷたの起源とするこの伝説は、彼が征夷大将軍として蝦夷制圧のため、
北東北に進軍した際、取り逃がして山の中に隠れてしまった蝦夷軍の大将をおびき出すために、
お祭りを催し、何事かと山から出てきた大将を捕らえることに成功したという話で、
この時のお祭りがねぷたの起源だというものだ。
けれども、このような田村麻呂を英雄とする伝説は、実は他にもある。
例えば、お隣の南部地方では、獅子舞で敵軍の大将をおびき出したという伝説があるのだ。
この手の話は、室町時代に書かれた田村麻呂を主人公とする
御伽草子の『田村草子』から派生したものであるらしい。
この伝説がねぷたの起源として今でも広く知られているのは、
青森ねぶた祭りのコンテストの最優秀賞が「田村麻呂賞」と名付けられていたためであろう。
この賞は田村麻呂が津軽地方まで遠征していないという歴史的事実と先住民族への配慮から、
平成8年に「ねぶた大賞」に改められた。
けれども、一度市民に広く知られた偽りの起源はそう簡単に消えて無くなるものではない。
そもそも、このような学術的に裏付けの無い伝説が、
コンテストの最優秀賞のネーミングにまで採用されたのはなぜであろうか。
おそらく事の起こりは、明治初めのねぷた禁止令にあるのではないかと私は考えている。
時の県知事に当たる権令の菱田重禧はねぷたを「蝦夷の野蛮な習慣である」として禁止令を出した。
天皇に権力を戻った時勢において、田村麻呂率いる朝廷軍に制圧された蝦夷の文化が許されるはずは無い。
それならばと、当時の頭の良い「ねぷた馬鹿」がねぷたの起源に田村麻呂を据えた。
かくして伝説がまるで真実のように振舞うようになったのではないだろうか。
ところで、私はこの伝説に根本的に不可解な点があると思う。
想像してみてほしい。
あなたが、田村麻呂に追われ命からがら山奥に逃げ込んだ蝦夷の大将だったならば、
敵軍のお祭りにつられて山から出てくるだろうか。
私ならば絶対に出てこない。
それが、捕虜が無理矢理やらされた蝦夷側の祭りであったならば、話は別であるが。
参考文献 藤田本太郎氏著作『ねぶたの歴史』
■ 続きはこちらをクリック ・・・ 第4回 津軽為信の大燈籠説