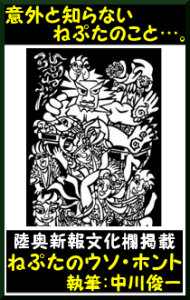弘前ねぷた祭りで、三年ほど前から物議をかもしているねぷたがある。
それは「八角ねぷた」と呼ばれる、ねぷたの土台部分が通常の四面ではなく、
倍の八面ある 八角形の土台をもつ人形ねぷただ。
このねぷた、弘前ねぷた祭り参加団体の「必殺ねぷた人」によって作られたものだが、
何を隠そう同団体の代表を務めるこの 私がデザインしたものである。
今回は、私事で恐縮だが、この「八角ねぷた」について書こうと思う。
私 は、造形美として四角よりも八角の方が良いからとかいう動機で、あれを考案したわけではない。
別に、六角でも十角でも良かった。
私は、今の市役所が作った 規定の範囲内で、何か新しいねぷたを考案したかったのだ。
ねぷたは人の手によって作られるものだ。
人形ねぷた、扇ねぷた共に造形美術としての側面を持って いる。
であるならば、創造性を奪われては良いものは作れない。
毎年作られるねぷたに何か新しい試みをしようとするのは、自然のことではなかろうかと思うのだ。
けれども、当然このねぷたに、「伝統」という壁が立ちはだかった。
「伝統的ではない」という理由から、「ねぷた」ではなく「前燈籠」という地位しか与えられ なかった。
けれど、もし、ねぷたにおける「伝統」が、ねぷたの形状にあったならば、
人形ねぷたの出現や扇ねぷたの考案といった新しい動きが許されるはずも なく、
角燈籠から進化することなんてなかったであろう。
私は、ねぷたにおける「伝統」は、形ではなく、ねぷたに関わる人間の心にあると思うのだ。
毎年、作られては壊されるというサイクルの中で、豊かな創造性を持った先達の作り手と、
それを支持した社会が、今のねぷた祭りを構築してきたのではなかっただろうか。
私はその問いを投げかけるために、「八角ねぷた」を考案し、祭りに参加している。
ところで、今年の弘前ねぷた祭りには、一つ嬉しい動きがあった。
奈良美智さんの版権が弘前ねぷたに限り開放され、
彼のポップな現代アートを題材にした燈籠に、「前ねぷた」の地位が認められたのだ。
この動き、扇動的ではあったが、私は賛同できた。