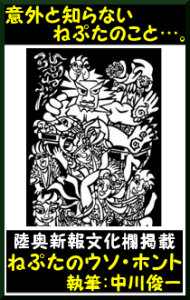9年ほど前から、弘前桜祭りに便乗して、
GWの時期に弘前で「春ねぷた」なるものが行われている。
おそらくは、桜祭りに集まった観光客にねぷたをアピールしようと言う
商業的な目的から始まったものであろうかと思う。
けれども、このアピールが本当に功を奏しているのかは、疑問が残る気がする。
そもそも、年に一 度の夏祭りを、春にもやってしまって良いものだろうか。
ねぷたは、年に一度の特別な非日常の時間であるから意味があると私は思うのだが。
このような弘前の動きには、やはり現在の主流が扇ねぷたであることが、関係していると思う。
以前にも述べたが、人形ねぷたに比べれば扇ねぷたは作業量が少ない。
このことが一年に何度もねぷた祭りを行うことを可能にしていると言える。
けれど、無節操に観光という目的だけでねぷた祭りを行うことには私はやはり賛同できない。
私は、この連載で何度か、「弘前の伝統は扇ねぷたではない」ということを述べてきた。
扇ねぷたは現在の弘前の主流であって、そればかりが伝統ではないと考えるからだ。
私が、なぜこのように今の時流に抗おうとするのか。
それはねぷたの文化性を考えたとき、扇ねぷただけでは片手落ちになってしまうと思うからだ。
扇ねぷたのメリットである「作業量が少ない」は、扇ねぷたの弱点でもあると思うのだ。
私は、ねぷた祭りの最大の特徴は「作る」ということにあると考えている。
そこから発生する意義役割が、現在の社会に必要だと考えている。
このまま、弘前ねぷたが扇ねぷたに傾倒し続け、「作る」という部分が減少していくと、
ねぷたの文化性は消滅してしまうのではないかと危惧している。
(扇ねぷたばかりが、ねぷたの文化性を消滅させる原因であると考えているわけではないが。)
もちろん、「春ねぷた」に関る方々のご尽力を何も考えないわけではないのだが、
先のように考えている私の目には、「春ねぷた」は、ねぷたの文化性の減衰を象徴しているように映り、
一抹の不安を覚えずにはいられない。
■ 続きはこちらをクリック ・・・ 第16回 「ねぷたのウソ・ホント」最終章