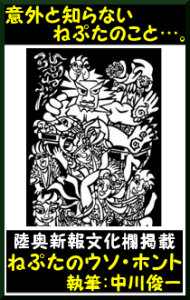今回は、書物の記録にねぷたが登場した江戸時代中期頃から、
昭和の初めまで続いた喧嘩ねぷたについて述べたいと思う。
喧嘩ねぷたとは、その名の通り、ねぷた運行に伴い生じる喧嘩のことであるけれど、
最初の頃は道で正面から出くわした二台のねぷたが互いに道を譲れと小競り合いをする程度だったが、
次第に激化し、明治の頃には町道場間の抗争にまで発展した。
この喧嘩ねぷたの習慣はねぷた祭りに二つの変化をもたらしたと私は考えている。
一つは、意義の変化である。
本来眠り流しを起源にもつねぷた祭りの意義は、「穢れ祓い(けがればらい)」あった。
それが喧嘩ねぷたの習慣によって、祭りの意は、特に武士階級の「うっぷん晴らし」へと変化したのだ。
けれども、「うっぷん晴らし」と「穢れ祓い」、この両者はまったく異なるとは言えないと思う。
うっぷん晴らしを現代の言葉で言い直すと、おそらく「ストレス発散」となるだう。
現代の医学ではストレスが体に多大な悪影響を及ぼすことがわかっている。
古代の眠り流しで祓われた穢れもストレスと同様に身体に悪害をもたらすものと考えられていたはずだ。
そう考えるとこの変化は許容できる範囲内の変化ではないだろうか。
もちろん喧嘩ねぷたの暴力的抗争に賛同するわけではないけれど。
そして、もう一つが、ねぷたで作られる題材の変化である。
現代では、全般的に、軍神や武将の退治や戦といった勇ましい題材が多いけれど、
江戸時代の後期までは、恵比寿や米俵そして千両箱といった縁起物が題材にされることの方が多かったのである。
それが江戸末期から明治の頃の、喧嘩ねぷたの激化と全国的な武者絵の流行を背に、
勇壮な題材が多く作られるようになり、現代に至っている。
この戦が求められた時代の題材の変化は自然のことであり、非難する気は無い。
けれど、戦争を求める人よりも平和を求める人が多いであろう今の時代では、
多少の違和感を覚える感じがするのは私だけだろうか。
まして、それが古くからの伝統ではなく、この百数十年の動きなのだから、なおさらそう感じてしまうのだ。
参考文献 藤田本太郎 著作『ねぶたの歴史」
■ 続きはこちらをクリック ・・・ 第12回 合同運行