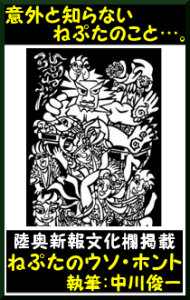今回は、歴史や技法から少しはなれて、
県立弘前高校が学園祭の一環行事として毎年七月中旬に制作運行している
通称「弘高ねぷた」のことを書きたいと思う。
弘高ねぷたの歴史は随分古く、五十年以上の歴史を持つ。
初期の頃は扇ねぷたでの出陣だったらしいが、
その後、人形ねぷたに変化し、現在でも人形ねぷたが制作されている。
(弘前の伝統が扇ねぷたばかりではないことは以前にも述べた。)
弘前高校のこの変化は、弘前市の人形ねぷたの減少と扇ねぷたの増加という時代の流れとは、
まったく逆の動きと言える。 なぜ弘前高校では人形ねぷたを制作するようになったのか。
それは、前回で述べた人形ねぷたの制作作業の特徴が関係していると思う。
彼らの制作意欲が、人形ねぷた制作の膨大な作業量の多さを上回っているのだろう。
現在、弘前高校では、二週間足らずで、一クラス一つの人形ねぷたを制作している。
一クラス四十人余りの手が、夢中になってねぷたを作っているのだ。
私は、「どこのねぷた祭りが一番好きですか?」と聞かれると、必ず「弘高ねぷた」と答える。
弘前ねぷた祭りよりも、青森ねぶた祭りよりも、弘高ねぷたが一番好きなのだ。
それには理由がある。
彼らは何事にもとらわれる事の無い自由な発想を持ち、
それを人形ねぷたと言う形にしているからだ。 それが素晴らしい。
彼らは、現代の祭りが抱えてしまった様々な足かせに自由を奪われるということがほとんど無い。
その自由奔放さは制作だけではなく運行においても同様である。
彼らに弘前の常識なんてものは通用しない。
「ヤーヤードー」とともに彼らは「ラッセラー」の掛け声をも用いて飛び跳ねる。
そのリズムを先導しているのが、なんと「サンバホイスッル」という二つの音を出せる
南米カーニバルで用いられる笛なのだ。
全てのクラスがこの笛を持ち、しかも弘前高校オリジナルの節まであるのだ。
この斬新で創造性溢れる彼らのねぷたが私はどのねぷた祭りよりも一番好きなのだ。
今年の運行は今日の六時半から。
今年も「ねぷた馬鹿」の卵たちの熱狂振りを見に街に繰り出そうと思う。
次回は再び歴史に戻って、かつての喧嘩ねぷたという習慣について述べたいと思う。